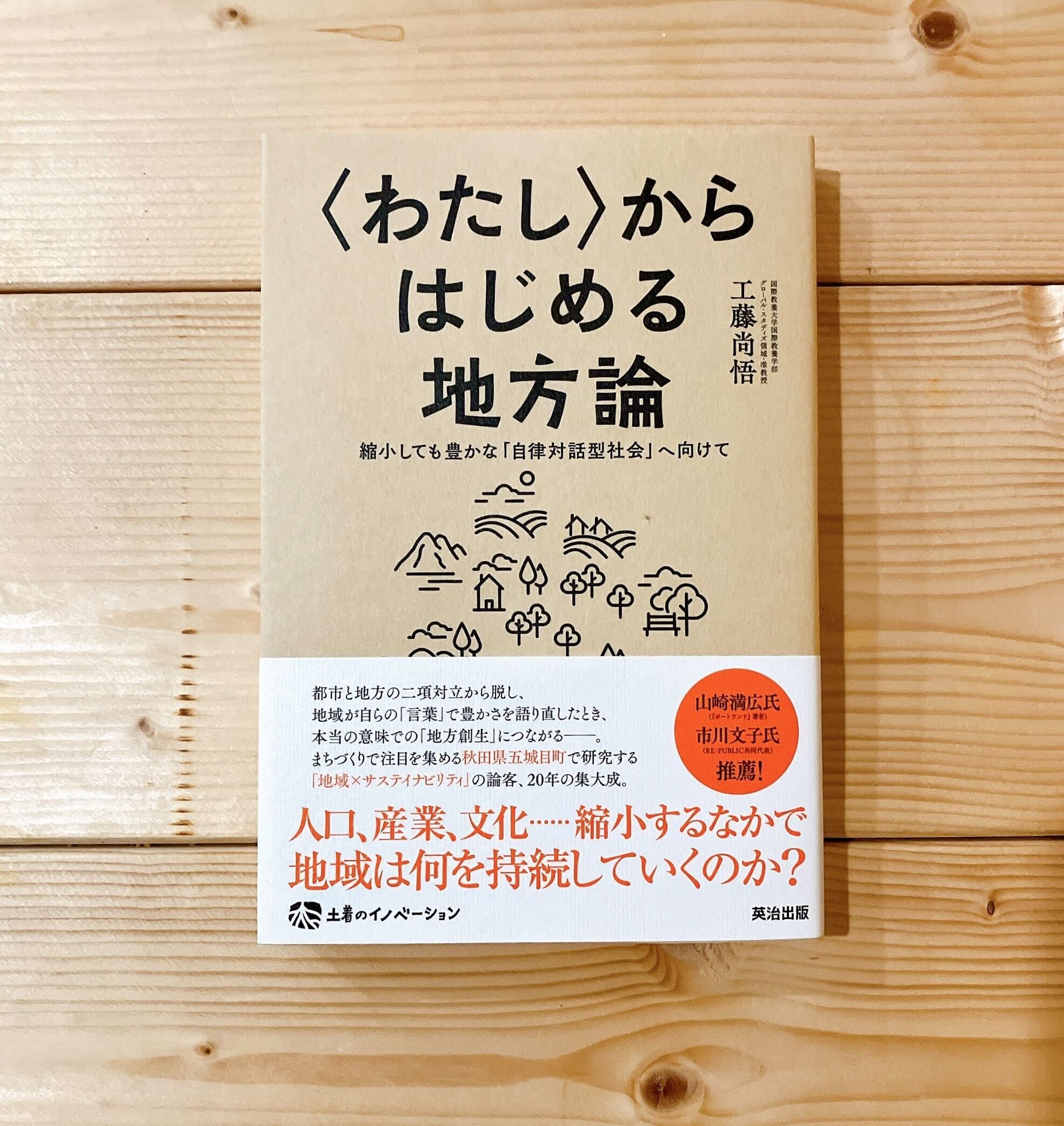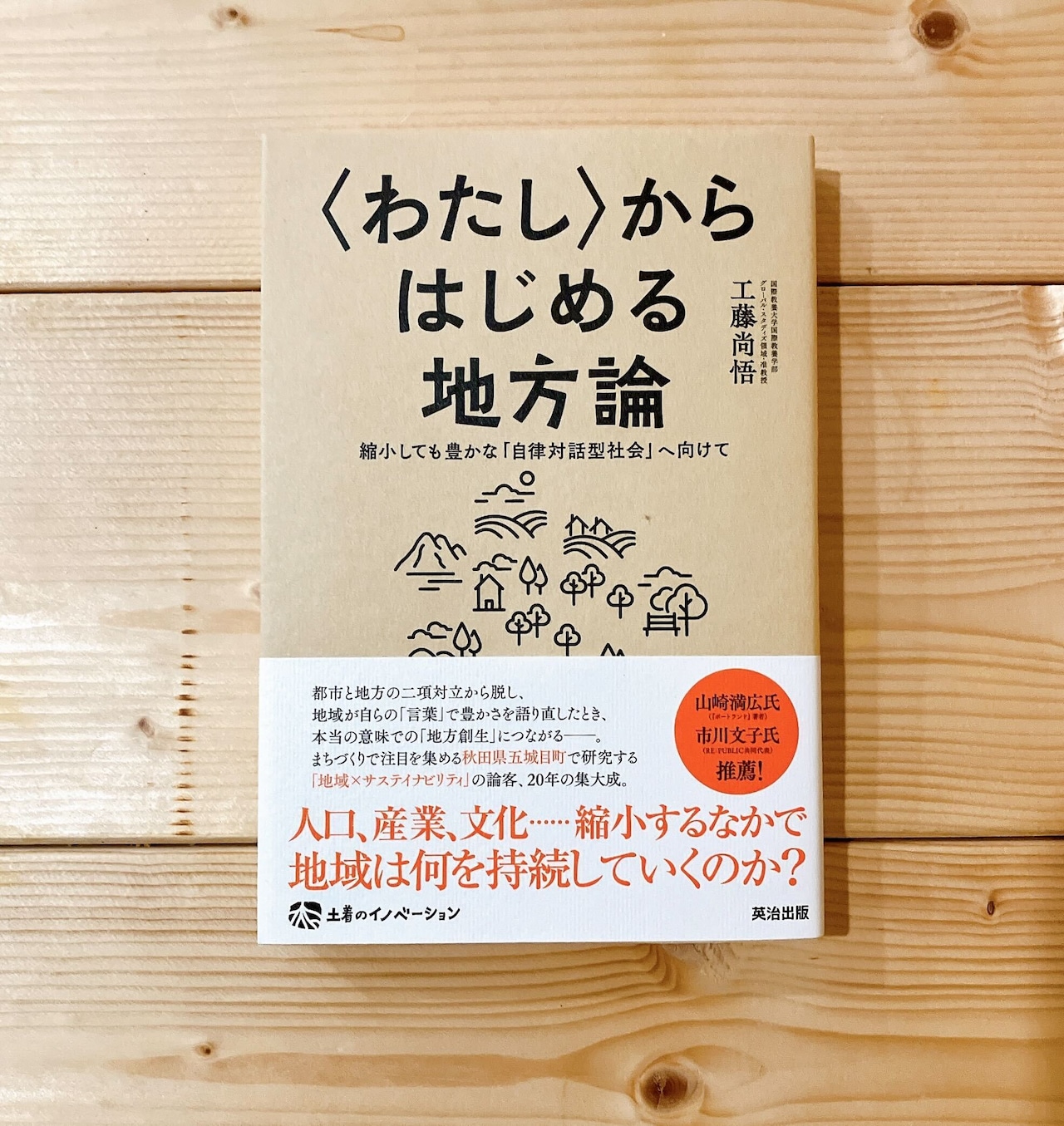
〈わたし〉からはじめる地方論――縮小しても豊かな「自律対話型社会」へ向けて/工藤尚悟
¥2,200 税込
残り1点
なら 手数料無料で 月々¥730から
別途送料がかかります。送料を確認する
¥10,000以上のご注文で国内送料が無料になります。
著者:工藤尚悟
出版社:英治出版
判型:四六版/280ページ
版元からの紹介:
人口、産業、文化……縮小するなかで
地域は何を持続していくのか?
都市と地方の二項対立から脱し、
地域が自らの「言葉」で豊かさを語り直したとき、
本当の意味での「地方創生」につながる──。
秋田県五城目町で研究する
「地域✕サステイナビリティ」の論客、20年の集大成。
■地域に「言葉」を取り戻すことが、なぜ必要なのか
「地域を活性化しなければ」
「限界集落での生活は、大変に違いない」
2014年の「地方創生」発表から10年が経ち、2025年6月には、石破内閣により地方創生2.0の基本構想が発表されました。「地方を盛り上げなければならない」はもはや疑う余地のないテーゼとなりつつあります。
本書『〈わたし〉からはじめる地方論』の著者である工藤尚悟氏は、この展開に待ったをかけます。
国際教養大学准教授で「地域×サステイナビリティ」について20年探究を行ってきた工藤氏は、「地域を巡っては、地域活性化といったポジティブな言葉から限界集落、消滅可能性都市といったネガティブな言葉まで、すべて中央から発信された言葉であり、都市と地方の二項対立を前提としている」と語ります。
そして、都市からの発信に偏った結果、地域は都市から人口をいかに獲得するかという議論に陥り、「言葉」を操る外部からくるコンサルタントに頼るしかなくなってしまうのだと。
■本当に問うべきは、「縮小していくなかで地域は何を持続していくのか」
では、本当に問うべきは何なのか。それを工藤氏は、「縮小していくなかで地域は何を持続していくのか」だと言います。
・地方創生と言うけれど、そこにはそのまちで暮らす人たちが何を持続するのかの視点が欠けている。
・消滅可能性都市と言うけれど、そこにはそのまちから何が消えると困るのかの視点が欠けている。
抜け落ちているのは、「その地域で暮らす〈わたし〉の視点」。本書では、地域というものを中央・都市と対置させるのではなく、訪れる人とそこで暮らす人が出会う流れのなかの〈あいだ〉という形で提示し、両者をフラットな関係でみることで、地域側からの「語り」が生まれる余地ができ、自律的な地域へと至ることが示されます。
■縮小と豊かさを両立する秋田県五城目町の5つの特徴を解き明かす
本書では五城目町で暮らす人たちが自分たちの暮らしのために企み、実行していったさまざまな取り組みが紹介されます。「縮小しても豊か」を実践するための5つの特徴(第4章)は必読です。
1)まちとつながる場所がある
・企業誘致ではなく多様な職種を集める――ババメベース……ほか
2)「小さな企て」が起きている
・仲間に背中を押されて生まれた「昼間のスナック」――いちカフェ……ほか
3)異質なものが流れ込む
・各地のローカルとの橋渡しの場――シェアビレッジ……ほか
4)自ら学ぶまち
・子どもの教育と大人の教育の境界線を越える――みんなの学校……ほか
5)誰かの「やってみたい」が具現化しやすい場がある
・数百円の出店料で挑戦できる――朝市plus+……ほか
■「土着のイノベーション」とは
社会の変容は、足もとの変容からしか生まれません。
そして、足もとの暮らしを変えていくには、
まちに、土地に、地域に根ざした「まなざし」こそが欠かせません。
地域に長く根を張り、世代を超えて持続的な変化をもたらす
「土着のイノベーション」ともいうべきムーブメント。
世界中で同時多発的に起こっているこの変化の「さざなみ」を、
あるときはその担い手に、またあるときは地域のエコシステムに、
さまざまな角度から光を当て、読み手の暮らしの変容へとつなげる。
そんな想いを実現すべく、英治出版が立ち上げたのが、
コンテンツレーベル「土着のイノベーション」です。
-
レビュー
(69)
-
送料・配送方法について
-
お支払い方法について